第5回アジアパラ競技大会の2026年秋の開催を前に、手助けが必要な人や不自由を抱えた人たちにも暮らしやすい街や困りごとについて考えていきたいと思います。できることは何か?を考え、身近にある体験からも学んでいきたいと思います。
障害を抱えた方が困っていること

障害などハンディキャップを抱えた方が困っていることを想像したことはありますか?今は、多くのテレビ番組などで取り上げられ可視化されている問題も多数あります。意識的にそういった知識を取り込もうとする気持ちだけでも一人一人が持っていることが誰もが生きやすい社会への第一歩だと思います。
例えば、四肢に障害を持たれた方が杖や車椅子を利用している場合、歩道に大きく飛び出して止めたれた自転車や、車などは一目して邪魔だということが分かると思います。そういった通行の妨げになる事は一人一人が気をつけることで無くすことのできる問題です。
視覚障害の方には点字ブロックのある歩道でも障害物があることで歩行の妨げになることがあります。
視覚・聴覚に障害をお持ちの方が困っていることに気づき援助できるよう声がけをすることは難しいことではありません。一歩を踏み出せれば、誰もが同じように助け合って生活していける社会になるのです。
目に見えない障害を抱えた方にも、思いやりの心を持って見守ることが大切です。困っていたら助けることはもちろんですが、むやみやたらに声をかけるのではなく、そっとサポートできる程度の距離感で見守ったり、不用意な発言を避けることが求められていると思います。
身近に起こった体験

障害を抱えた方と接する機会が多い人もいれば、ほとんど出会わず過ごす人もいる中で、たまたま公共機関で困っている方に出会った時、何ができるのか?知識もないまま手を貸すことが迷惑になるのではないか?と行動出来ないこともままあると思います。さらに恥ずかしさや、断られた時など想定外の反応に戸惑う事も要因となり、行動に移せない場合はあるかと思います。ただ、それはうちに向いた自分自身の気持ちに過ぎず、良かれと思った事が迷惑になる場合もあれど、躊躇なく手を差し出すことができる社会が本来の姿ではないかと思います。
そんな思いも持ち合わせながらも普段から困っている人の手助けをしたいと考えていました。そんな時に、ヘルプマークをつけたおじいさんがいらっしゃいました。何気なく目をやると、その方は杖をついてサングラスをしています。おそらく目の不自由を抱えておられるのだと感じました。さらによく見ると、耳も不自由であることを知らせるプレートをかけておられます。そして、飲食スペースの間を歩いている間に何度も椅子に足をぶつけていたのです。これはお助けしたいと近づき、お声がけをしました。そっと隣から覗き込みゆっくりと、「こちらに座って下さい」と言って腕を取り椅子へ案内しました。伝わっていなかったら怖い思いをさせたかもしれないと一瞬躊躇しましたが、その方は、「ありがとう」と手話でお答えくださいました。少しすると同行者の方が近づいてきたので一安心し、その場を離れましたが、何が正解だったのかもわからないまま、自己満足のような気持ちで一杯となったのも事実です。声が届いていなかったら、知らない人に腕を取られて怖い思いをしたのではないか、腕を掴んだ力が強かったら申し訳ない、そもそも必要ではなかったかもしれない。そんな思いもまた湧き上がってくるのです。普段からそういう場面に慣れていない者からすると、失礼にあたることすらもわからないこともあります。
しかし、何もしなかったら転んでいたかもしれない、そう思えばこれで良かったのだとも思えるのです。
そういった状況に何度か遭遇するもうまく対処できたのか不安に駆られることは少なくありません。それでも、何もしない、見て見ぬふりをする社会であって欲しくないと思うので、これからも行動し続けたいと思うのでした。
まとめ
ハンディキャップを抱えた人たちについて考える機会が多くなってきましたが、まだまだ実際に援助を躊躇なく行える環境ではないことも現実問題として挙げられています。知識がなかったり、コミュニケーションに不安を持ったりと、目に見えない問題の方が妨げになっています。以前、下校中の小学生たちがお子さん連れのお母さんのベビーカーを運ぶお手伝いをしているのを目撃しました。義務教育の段階で困っている人を援助することができる知識と気持ちを当たり前のこととして教えていけることも大切だと感じます。
困っている人がいたら助ける、困ったことがあったら助けを求めても良い、そんなことを当たり前に考え行動できる社会が当たり前のように訪れることを願っています。


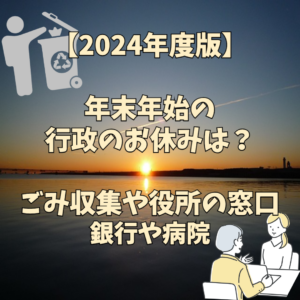




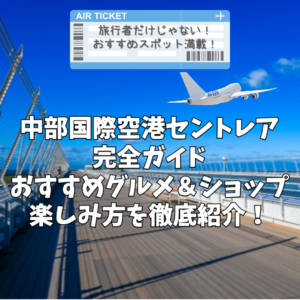

コメント